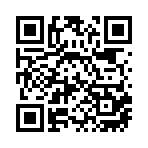CATEGORY:海軍 一種軍装
2016年01月19日
日本海軍 兵軍衣袴(昭17制)
みなさまお久しぶりでございます。
無事センターが轟沈した為、更新を再開させていただきます!!!!!!!(ヤケクソ)



おなじみの水兵服です。ジョンベラとも言われますね(中着襟単体がジョンベラと言われたりもします)。軍衣、軍袴とも両腰に洗濯後干す際に紐(洗濯ストップといいます)を通す鳩目が付いています。その為の鳩目は襦袢類にもありますが、共々末期になるとループへと省略されます。

裏返した写真。明治期と異なり(おいおい明治の卒軍服も紹介したいと思います)、全面に黒綾木綿が貼られ総裏になっております。

この襟の周りの釦は中着襟を止める為のものです。
胸の内側には二つポケットがあります。軍衣袴を着ている場合、物入れはこの二つと軍袴に一つ(後述)の計三つしか有りません。ポケットハンドは出来ませんね。(昭和7年始のら海軍服制ではまだ表隠シが存在していることになっています。[下図])



記名布。再用品の為通常は襟の裏にある記名布が右脇腹に移動しています。
続いて兵軍袴です。


塗料による汚れがやや目立ちます。

裾の踵部分には擦り切れ防止の為の補強が縫い付けられています。

明治の頃から長らく編上式で調節していましたが、開戦後の改正で腰紐式に変更され、中央の角釦も縦3つから2つに減らされました。
腰部ボタン→腰紐→前開きの順に閉じていくのが一般的ですが、稀に前開きの上から腰を縛っている人も見受けられます。
右足側にある布がポケットです。

角釦は虫食いまみれで、一つに至っては一欠片しか残っていません。美味しくいただかれています…。

記名印。こちらも再用品です。軍衣と同一の方の記名が入っています。
軍衣袴は昭和十七年の給与令では1人につき三組支給されることになっています。
が!!!昭和十八年十二月の海軍給与令施行細則によれば一人一組にまで減らされています。
(勘のいい人は年月で気づかれたと思いますが、これは略衣袴の制定によるものです。事実夏衣袴・軍衣袴等が大幅に減らされた一方、略衣袴は三組貸與されることになっています。)
揃いで買えてよかった…。
蛇足かもしれませんが畳み方です。

①前側に右側を畳み込む

②同様に左側も畳み込む

③方形になるように畳む

海軍では被服を衣嚢に収納する為このような畳み方をします。
無事センターが轟沈した為、更新を再開させていただきます!!!!!!!(ヤケクソ)



おなじみの水兵服です。ジョンベラとも言われますね(中着襟単体がジョンベラと言われたりもします)。軍衣、軍袴とも両腰に洗濯後干す際に紐(洗濯ストップといいます)を通す鳩目が付いています。その為の鳩目は襦袢類にもありますが、共々末期になるとループへと省略されます。

裏返した写真。明治期と異なり(おいおい明治の卒軍服も紹介したいと思います)、全面に黒綾木綿が貼られ総裏になっております。

この襟の周りの釦は中着襟を止める為のものです。
胸の内側には二つポケットがあります。軍衣袴を着ている場合、物入れはこの二つと軍袴に一つ(後述)の計三つしか有りません。ポケットハンドは出来ませんね。(昭和7年始のら海軍服制ではまだ表隠シが存在していることになっています。[下図])



記名布。再用品の為通常は襟の裏にある記名布が右脇腹に移動しています。
続いて兵軍袴です。


塗料による汚れがやや目立ちます。

裾の踵部分には擦り切れ防止の為の補強が縫い付けられています。

明治の頃から長らく編上式で調節していましたが、開戦後の改正で腰紐式に変更され、中央の角釦も縦3つから2つに減らされました。
腰部ボタン→腰紐→前開きの順に閉じていくのが一般的ですが、稀に前開きの上から腰を縛っている人も見受けられます。
右足側にある布がポケットです。

角釦は虫食いまみれで、一つに至っては一欠片しか残っていません。美味しくいただかれています…。

記名印。こちらも再用品です。軍衣と同一の方の記名が入っています。
軍衣袴は昭和十七年の給与令では1人につき三組支給されることになっています。
が!!!昭和十八年十二月の海軍給与令施行細則によれば一人一組にまで減らされています。
(勘のいい人は年月で気づかれたと思いますが、これは略衣袴の制定によるものです。事実夏衣袴・軍衣袴等が大幅に減らされた一方、略衣袴は三組貸與されることになっています。)
揃いで買えてよかった…。
蛇足かもしれませんが畳み方です。

①前側に右側を畳み込む

②同様に左側も畳み込む

③方形になるように畳む

海軍では被服を衣嚢に収納する為このような畳み方をします。